こんにちは。放射線などについて分かりやすく解説している大地(だいち)です。
現在、国が進めている、除染で発生した土の減容や再生利用等に対する、IAEAのレビューに関して、こちらの記事で、国際原子力機関(IAEA)が進めているレビューの背景等、こちらの記事で、IAEAによる全般的な評価について説明しました。
今回からは、そのレビュー内容について、各章に記載された、私なりのより詳細な解釈を解説していきたいと思います。
今回は、最終報告書の「第Ⅲ章:規制的側面」について説明したいと思います。
つまり、今回は、
・ 除去土壌の再生利用等に関するIAEAの最終報告書に書かれた「規制的側面」って何?
・ IAEA最終報告書は「規制的側面」についてどんな評価をしたの?
こういった疑問に答えます。
○本記事の内容
- 除去土壌の再生利用等に関するIAEA専門家会合最終報告書について(その3)
- IAEA最終報告書に書かれた「規制的側面」とは
- IAEA最終報告書「第Ⅲ章:規制的側面」に書かれた評価
- セクションⅢ.1 全体的なプロセス
- セクションⅢ.2 除去土壌の再生利用及び最終処分方法の正当化
- セクションⅢ.3 放射線防護における最適化の適用
- セクションⅢ.4 再生利用に関する省令及び技術ガイドラインの整備
- セクションⅢ.5 規制機能の独立性
- まとめ
この記事を書いている私は、2011年の福島第一原子力発電所の事故の後、除染や中間貯蔵施設の管理など、継続して放射線の分野での業務に従事してきました。
その間、働きながら大学院に通い(いわゆる社会人ドクター)、放射線の分野で博士号を取得しました。
こういった私が、解説していきます。
除去土壌の再生利用等に関するIAEA専門家会合最終報告書について(その3)
それでは早速、最終報告書の「第Ⅲ章:規制的側面」に書かれた内容について見ていきましょう。
IAEA最終報告書に書かれた「規制的側面」とは

「規制的側面」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、簡単に言うと再生利用や最終処分に関する制度に関すること、と理解できるかと思います。
具体的には、その実施の基礎となる放射性物質汚染対処特措法や、関連する政令、省令、そしてガイドラインなどの文書だけでなく、組織体制やその運用方法なども対象となっています。
2025年度以降に予定されている、より大規模な再生利用事業の実施に必要となる、放射性物質汚染対処特措法の省令の改正と、技術ガイドラインの策定が2024年度末までに実施されることとなっており、この点については、最終報告書でも何度も言及されています。
IAEA最終報告書「第Ⅲ章:規制的側面」に書かれた評価
以下で、各評価項目について解説していきますが、説明のための利便性の観点から、各評価項目についてアルファベット(a, b, c…)を付しています(実際の報告書には書かれていません)。
セクションⅢ.1 全体的なプロセス

最終報告書にも書いていますが、「8つのステップ」とは、中間貯蔵施設等に係る対応について(2014年8月8日)に書かれた、福島県外での最終処分の完了に向けた今後の方向性を示したものです。
大まかに分けると、ステップ1〜4が最終処分の実現に向けて必要な技術の開発など、基盤となる部分の整備、ステップ5〜8が最終処分地の候補選定やその建設などの具体的な方策になります。
ここでは、規制的側面についても、この工程に沿って、顕著な進展があった、と評価されています。
2025年度以降により本格的な事業の実施に移行することを考慮すると、2024年度末までにステップ4を完了させ、2025年度以降にステップ5以降の工程が開始される、と言いかえることもできるでしょう。
こちらの記事でも解説したように、2025年度以降の再生利用の本格的な実施に向けて、2024年度末までに、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略に基づいて実施されてきた技術開発の成果などが取りまとめられる予定になっています。
ここでは、「再生利用に関する省令」と「最終処分に関する省令」が分けて表現されていますが、実際には、放射性物質汚染対処特措法施行規則が改正され、その中で再生利用に関する基準と、最終処分に関する基準が分けて書かれることになるかと思います。
最終報告書のセクション「Ⅳ.3 – 減容技術」にも書かれていますが、現在、将来的な最終処分量を減らすため、減容に関する様々な技術(例:分級、焼成)が検討されているところです。
基本的には、これらの成果は2024年度末までに取りまとめられることになっており、2045年3月までの最終処分完了に向けて、その選択肢の検討もいずれ完了させるべき、という助言かと思います。
セクションⅢ.2 除去土壌の再生利用及び最終処分方法の正当化

この「正当化」については、こちらの記事でも解説しましたが、放射線防護の三原則のうちの一つで、放射性物質を取り扱う上で最も重要な考え方の一つです。
簡単に言うと、放射線を使う行為は、それによってもたらされる便益が、放射線の使用による不利益を上回る場合にのみ認められる、という考え方なのですが、これは当然、福島第一原子力発電所の事故によって発生した放射性物質を取り扱う上でも適用されます。
最終報告書にも書かれていますが、こうした取組を行うことによる便益とは、被災地に住む住民等への放射線によるリスクの低減、避難指示の解除などを通じた被災地の復興への貢献が挙げられるでしょう。
一方で、不利益とは、こうした事業に携わる作業員への放射線被ばくだったり、放射線防護に直接関わらないような要素、例えば、除去土壌の輸送や管理に伴う人的、また経済的・社会的なコストなども考えられるでしょう。
ここでは、その放射性物質を含んだ除去土壌の再生利用及び最終処分の取組によりもたらされる便益が、その取組により生じる不利益を上回っており、取り組む価値がある、と評価されているということです。
ちなみに、「SF-1」とは、「Safety Fundamentals-1」のことで、こちらの記事でも解説した、安全基準の一つである、安全原則のことです。
これはこうした事業を行う上での前提となる考え方であり、重要な評価であると思います。
「SF-1」とは、上の「d.」のポイントでも示したように、安全原則のことです。
この安全原則には10の原則があるのですが、再生利用に関する取組が、その7番目:「現在及び将来の世代の防護」の中で書かれている、「放射性廃棄物の発生は、物質の再利用と再使用のような適切な設計上の対策と手順によって実現可能な最小限の水準に維持されなければならない。」という考え方に合致している、と評価されています。
セクションⅢ.3 放射線防護における最適化の適用
この放射線防護における「最適化」についても、こちらの記事でも解説しましたが、放射線防護の三原則のうちの一つで、放射性物質を取り扱う上で最も重要な考え方の一つです。
このポイントでは、評価というよりも、この放射線防護(と安全)の最適化に関する解説を行っています。
この最適化は、こちらの記事でも触れましたが、より簡潔に言うと、放射線防護上の観点からだけではなく、他の要因(例:社会的要因、経済的要因)なども考慮した上で、合理的に達成可能な限り(ALARA)被ばく線量を低くしましょう、ということです。
最終報告書では、この「最適化」は放射線防護に関する基準や水準を決めるプロセスであり、「ALARA」はそのプロセスで決定された結果である、と解説されています。
この再生利用事業においては、この事業に関連して、作業者及び周辺の住民が受ける追加的な被ばく線量を1mSv以下にすることとしています。
こちらの記事でも解説したように、日本人が1年間に受ける全ての被ばく線量は約6mSv(その内自然界からは約2.1mSv)なので、1mSvは多いと感じられる方もいるかもしれませんが、例えば、農地に関する再生利用事業では、被ばくが最も大きくなると思われる、農地の造成に関わった作業者の8ヶ月間の被ばく線量が0.096~0.143mSvとなっていますので、周辺の住民については、これよりも遥かに低い値になることが想定されます(出典:中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループ(第4回)資料2−1)。
また、こちらの記事でも解説した、被ばく線量と人の健康への影響との関係を見ても、こうした被ばく線量が、人の健康に影響を及ぼすようなレベルのものではないこともお分かりいただけるかと思います。
最適化というのは、経済的、社会的、環境的要素も考慮に入れ、合理的に達成可能な限りにおいて、極力被ばく線量の低減を目指すものですので、飛散流出防止の目的のための覆土等により、線量を下げることはIAEA安全基準に合致した取組とされています。
具体的には前述した安全原則の「原則5:防護の最適化」にその内容が書かれています。
また、その最適化の取組を通じて目指すべき線量水準は、関係するステークホルダーと相談の上決定されるとの認識が示されています。
この水準は、一度達成されたら良いというものではなく、合理的に達成可能な範囲において、繰り返し見直されるもの、というのも留意したい点です。
ここでは、放射線防護と安全に関する最適化に関して、「f.」 のポイントで示したような説明とともに、その水準は年間10μSvのオーダー以下である必要はないことも示すべきである、としています。
この「年間10μSvのオーダー以下」というのは、放射性廃棄物の「クリアランス」、つまり放射性物質に関する一切の規制から除外され、他の物と同様に、自由に流通できるとされる追加的な被ばく線量のことですが、最適化というのは、必ずしもこのクリアランスレベルを目指すものではないことを示すべき、ということが書かれています。
セクションⅢ.4 再生利用に関する省令及び技術ガイドラインの整備

放射性物質を扱う事業において、その利用による被ばく量を事前に評価することは、「d.」 で述べられた「正当化」や、「f.」 で述べられた「最適化」などを検討する上で重要な作業になります。
この再生利用に関する事業においても、この被ばく線量評価が行われ、専門家会合の場で議論されたものと思われますが、まずその手法(例:被ばく経路の設定、パラメータの設定方法)が十分に保守的(安全側に立って)評価されている、ということが述べられています。
その後で言及されている「スクリーニングレベル」とは、「IAEA一般安全指針18(GSG-18):クリアランスの概念の適用」で登場する、放射性物質に関連した施設の事故などの後の環境回復事業で発生する廃棄物の再生利用に関連する値のことで、「h.」で述べられた「クリアランスレベル」とは区別する必要がある概念です。
ちなみに、福島第一原子力発電所の事故後の環境回復事業に伴って発生する土壌の再生利用についても、このGSG-18において具体的事例として取り上げられています。
ここでは、この8,000Bq/kg以下という放射能濃度(スクリーニングレベル)の土壌を用いることで、この目標となる線量基準(1mSv/y)は十分に達成可能と評価しています。
前述したように、2024年度末までに、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略に基づいて実施されてきた技術開発の成果などが取りまとめられ、再生利用事業の本格的な実施に向けて、放射性物質汚染対処特措法の施行規則(環境省令)の改正と技術ガイドラインの策定が予定されています。
この省令と技術ガイドラインの内容についても、専門家会合で議論されたものと思われますが、その内容については、建設期間及び再生利用のための構造物建設後の維持管理期間において、安全を保証するために必要な要素を網羅していると評価されています。
ちょっと難しい内容になっていますが、ここでは再生利用事業に関する長期的な安全性に関する評価の重要性について述べられています。
放射性物質の壊変によって、放射能濃度は時間の経過とともに減少します。
こちらの記事でも解説しましたが、福島第一原子力発電所の事故の場合は、現在環境中に残留している主な放射性核種はセシウム134や137で、この内、セシウム134は物理学的半減期が約2年であり、その影響は事故当初と比べるとかなり低減していて、今後は残留する主たる放射性核種は物理学的半減期が約30年のセシウム137になっていきます。
そのセシウム137による影響も、遠い将来には、その影響を無視することが可能となる時期が来るわけで、その時期の見定めを含めた、放射線防護上の観点からの長期的な評価の重要性と、環境省が既にその検討を始めていることが述べられています。
この最終報告書にも何回か書かれていますが、この再生利用事業は、日本の法律において責任体制が明確となっている機関(公的機関等)による適切な管理の下で実施されることになっています。
こうした公共機関等が事業の実施者になり、環境省がその制度を管理し、必要な助言等を行う、というのが基本的な役割分担になります。
ここでは、どのような状況や事態(通常時の管理のほか、災害等の非常時)が発生した場合に、事業の実施者が環境省にどのように報告し、環境省がそれに対して助言等を行うのか、そのプロセスが、今後策定される技術ガイドラインや協定に明記されるべき、と指摘されています。
通常時もそうですが、やはり、周囲の住民の方々などが懸念するのは、災害などが発生して、内部にある除去土壌等が外部に流出した場合の対応かと思います。
もちろん、そういう事象が発生しないように事前に十分な対策を取る必要がありますが、それでも起こってしまう不測の事態への対応も検討しておく必要がある、ということかと思います。
2つ上の「l.」 でも触れましたが、時間の経過とともに放射能濃度は下がるため、いずれ訪れる、特別な管理が不要になる時点について検討を進めておく必要性に言及されています。
この放射線防護上の観点からの「特別な管理」の具体的な内容については、ここでは述べられていませんが、おそらく定期的なモニタリングなどが想定されるのではないかと思います。
それを終了するということについては、その周囲の住民の方々などの不安につながる可能性もあるため、慎重かつ段階的に検討を進める必要がある、とされているのだと思います。
ここで言う「事業」はもちろん再生利用に関する事業のことかと思いますが、その実施前に、この事業に関連する人たちと場所固有の協定を作成すべき、とされています。
後の章でも述べられていますが、協定に関する一般的なひな形のようなものも提供することが提言されていますが、事業実施場所によって、土地の利用形態、地形、社会的背景などが多様であることから、その場所の状況に応じた協定が策定されるべき、と指摘されているのだと思います。
また、土壌の受入基準についても、その用途(例;農地、道路盛土)によって品質等が大きく異なることが予想されることから、その協定に明記されるべき、とされているかと思います。
前述したように、2024年度末までに、再生利用事業の本格的な実施に必要となる、省令の改正及び技術ガイドラインの策定が予定されています。
省令には、法文と言うその性質上、あまり詳細な内容は書かれないでしょうが、それを補完する技術ガイドラインには、比較的様々な内容を盛り込むことができると考えられます。
ここでは、当然必要となる技術的事項以外にも、管理体制や、コミュニケーションの重要性についても記載されるべき、と書かれています。
より詳しくはセクションⅥに関する記事で解説したいと思いますが、除去土壌等の再生利用及び最終処分に係る地域社会における社会的受容性の向上を目指して、地域とのコミュニケーションや地域共生のあり方等について検討を行うため、中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会の下に、「中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用及び最終処分に係る地域の社会的受容性の確保方策等検討ワーキンググループ」が2024年1月に設置され、議論が続けられています。
再生利用等を進めるためには、技術的な課題に加えて、事業と地域共生のあり方など、社会的な課題も解決していく必要があります。
ここでは、その重要性を、2024年度内に策定予定の技術ガイドラインにも明記すべき、と書かれています。
ここで述べられている「望ましくない事態」とは、おそらく、例えば、自然災害などで構造物が損傷し、その内部で使用されている除去土壌が外部に流出する事態のことを想定していると思われます。
「m.」 でも似たようなことが書かれていますが、こうした不測の事態が発生した場合の具体的な手順が技術ガイドラインに明記されるべき、ということです。
日本では近年地震や豪雨による災害が頻発しています。
もちろん構造物に被害が生じないことが一番ですが、万が一起きてしまった場合に対する備えにも万全を期すべき、ということかと思います。
セクションⅢ.5 規制機能の独立性

2011年3月の福島第一原子力発電所の事故以降、放射性物質汚染対処特措法に基づき、特に除染特別地域(こちらの記事も参照してください)については、環境省が直接事業実施者となり、除染を進めてきました。
国際的な考え方に照らせば、環境の汚染を引き起こした直接の原因者である東京電力がオフサイトの除染についても実施すべきですが、そうしなかったのには、例えば、以下のような理由があると思います。
・汚染された地域の住民等の被ばく線量の低減は喫緊の課題であった中、汚染された全ての地域を除染するには、東京電力一社では体制・人員等が十分とは言えなかった。
・国にも、原子力政策を推進してきた社会的責任があった。
こうした状況も勘案した結果、ここでは、事故後、このオフサイトの除染について、環境省が事故後、規制者と事業実施者の両方の役割を担ってきたことは適切である、と評価していると考えられます。
こちらの記事でも解説した、安全原則に書かれた10の原則のうち、「原則2:政府の役割」にはこのように書かれています。
独立した規制機関を含む安全のための効果的な法令上及び行政上の枠組みが定められ、維持されなければならない。
(参照:IAEA安全基準邦訳データベース (安全原則)(旧原子力安全基盤機構)より)
一つ前の「s.」 の指摘で述べられているように、これまでの環境省の状況は適切であったとしつつも、ここに明記されているように、今後は規制機能は事業実施機能から独立させるべきである、とされています。
事故から13年以上が経過した中で、規制機能を事業実施機能から独立させるべき時期が来ている、ということなのかもしれません。
そして、そのことが、長期的な安全性の向上や、国民及びステークホルダーの信頼の向上に役立つ可能性がある、とされています。
「r.」 でも指摘された意思決定手順(例:不測の事態が発生した場合の、事業実施者から規制者への報告手順、規制者から事業実施者への助言の手順)を策定することにより、規制者がどこでその機能を発揮できるかが明確になる、としています。
また、その独立性の示し方については、他の機関にその機能を持たせるだけでなく、環境省内でその機能を分離することも選択肢の一つとしています。
環境省の中には局、課などの部署がありますし、地方支分部局(地方環境事務所)もあります。
どういう分け方をしても良いが、「機能」としては明確に分離すべき、という助言かと思います。
まとめ
今回は、除去土壌の再生利用等に関するIAEA専門家会合最終報告書に関して、「第Ⅲ章:規制的側面」に書かれた結論の内容について解説しました。
IAEAの安全原則にも書かれている、放射線防護に関する非常に重要な考え方に合致している旨の評価がされている一方で、規制機能の実施機能からの分離など、今後の本格的実施に向けて重要な指摘もあり、継続して対応することが求めれます。
本記事の英語版はこちらからご覧いただけます。
今回は以上となります。
ご覧いただき、ありがとうございました。

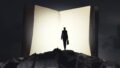

コメント