こんにちは。放射線などについて分かりやすく解説している大地(だいち)です。
皆さんは「除染特別地域」「汚染状況重点調査地域」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
除染が行われた地域は大きくこの2つに分けられ、その実施主体などが異なっています。
今日は、
・「除染特別地域」「汚染状況重点調査地域」ってどのような地域なの?
・除染は、どのような役割分担に基づいて、誰が主体となって行われたの?
こういった疑問に答えます。
○本記事の内容
- 除染特別地域と汚染状況重点調査地域について
- 除染の実施主体に関する基本的な考え方
- 除染特別地域
- 汚染状況重点調査地域
- 今後の両地域の方向性
- まとめ
この記事を書いている私は、2011年の福島第一原子力発電所の事故の後、除染や中間貯蔵施設の管理など、継続して放射線の分野での業務に従事してきました。
その間、働きながら大学院に通い(いわゆる社会人ドクター)、放射線の分野で博士号を取得しました。
こういった私が、解説していきます。
除染特別地域と汚染状況重点調査地域について

(出典)環境省ホームページ(2025年10月1日アクセス)
まずは、二つの地域の場所から確認してみましょう。
上の地図中、除染特別地域は、オレンジ色の線で囲まれた地域です。
灰色の地域(帰還困難区域)は全て除染特別地域に含まれており、その帰還困難区域内にある明るい緑色の地域(特定復興再生拠点区域)や、濃い青色の地域(特定帰還居住区域)も、当然除染特別地域に含まれています。
福島県内にあって、福島第一原子力発電所のごく近傍に位置していることが分かります。
一方、汚染状況重点調査地域は、それ以外の地域で、黄緑色や黄色の地域です。
北は岩手県、宮城県、そして、福島県内の除染特別地域以外の地域、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県に分布していることが分かります。
黄緑色はその時点で、依然として汚染状況重点調査地域に指定されている地域、黄色は過去に指定されていたが、現在では指定が解除された地域、ということになります。
除染の実施主体に関する基本的な考え方

それでは、除染特別地域と汚染状況重点調査地域は、どのような考え方に基づいて地域分けされているのでしょうか。
まず、除染特別地域は、当該地域を設定した時の避難指示区域(元の警戒区域及び計画的避難区域)とほぼ一致していたことを抑えておきましょう(楢葉町の一部のみ、避難指示区域でなかった箇所も除染特別地域になっていますが、それ以外は一致しています)。
避難指示区域の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
この地域については、福島第一原子力発電所の事故によって住民もさることながら、行政機能も合わせて移転を余儀なくされた地域です。
このことから、地元市町村が除染特別地域において除染事業を行える可能性はかなり低かったと言えます。
これに加えて、原子力行政を推進してきた国の社会的責任も考慮して、除染特別地域では、国(特に環境省)が除染事業を担当しています。
一方、汚染状況重点調査地域では、地域の事情に精通している地元の市町村が除染事業を担当し、国が技術的、財政的な支援を行うこととされています。
なお、福島第一原子力発電所を運転してきた東京電力については、除染事業の直接の実施者とはなりませんでしたが、これは、福島第一原子力発電所の廃炉作業等に人員をかける必要があること、放射性物質による汚染が東北地方から関東地方にかけて広がっており、一つの会社が担当するにはあまりに広範囲だったこと、などが理由として挙げられます。
この役割分担の在り方については、事故当初も色々と議論がありましたが、これについては、また機会があればご説明したいと思います。
それぞれの地域のより詳細な情報について、以下に説明したいと思います。
除染特別地域

除染特別地域については、既に述べたように、福島第一原子力発電所の近傍にあり、長らく11市町村(大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、楢葉町、川内村、田村市、葛尾村、南相馬市、飯舘村、川俣町)がその指定を受けてきました。
この内、田村市については、市内にあった汚染状況重点調査地域と合わせて、2022年3月にその指定が解除され、2025年9月時点では10市町村となっています。
これらの市町村では、指定後に避難指示が解除された市町村でも、国(主に環境省)により、必要な除染事業(発生した土や廃棄物の管理を含む)が行われてきました(除染の具体的な工程については、こちらの記事をご覧ください)。
除染特別地域における面的な除染については、帰還困難区域を除いて2017年3月末までに終了しており、その後はモニタリングや、必要なフォローアップの除染が行われています。
その後、帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能とする特定復興再生拠点区域の整備が行われ、当該区域では、2023年11月までに全ての避難指示が解除されました。
詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
その後、帰還困難区域内において、特定復興再生拠点区域外で、避難指示解除による住民による帰還及び生活再建を目指す区域として「特定帰還居住区域」の整備が2023年12月から始まっています。
帰還困難区域における今後の課題も含め、詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
汚染状況重点調査地域

汚染状況重点調査地域は、除染特別地域と比べると、福島第一原子力発電所からは遠い地域に分布しており、既に述べたように、北は岩手県、南は埼玉県や千葉県にまであります。
汚染状況重点調査地域は基本的に市町村単位で指定されますが、福島県にある田村市、川俣町、川内村、南相馬市については、除染特別地域と汚染状況重点調査地域の両方の地域が同一市町村内にあります(田村市については2022年3月に指定解除)。
この汚染状況重点調査地域の指定については、その根拠法となっている放射性物質汚染対処特措法に、0.23μSv/h以上の空間線量率を有する地域があって、更に重点的な調査が必要な地域とされていて、関係する自治体の意見を聞いて指定することとされています。
この0.23μSv/hという空間線量率については、また別途解説をしたいと思います。
汚染状況重点調査地域における面的な除染については、2018年3月末までに終了しており、その後は、除染特別地域と同様、モニタリングや、必要なフォローアップの除染が行われています。
ちなみに、2012年1月に両地域の根拠法となっている放射性物質汚染対処特措法が完全施行された際、その数は102で、その後2012年2月に福島県柳津町と宮城県亘理町が追加で指定され、最大104市町村になりました。
その後、除染の進捗や時間経過などにより空間線量率が低減したことなどを受けて、徐々に指定が解除されており、2025年9月末時点で64となっています(出典:除染情報サイト)。
詳細については、下の表をご覧ください。
| 県名 | 市町村数 | 汚染状況重点調査地域に指定されている市町村(令和7年9月30日時点) |
|---|---|---|
| 岩手県 | 3 | 一関市、奥州市、平泉市 |
| 宮城県 | 7 | 白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町 |
| 福島県 | 9 | 南相馬市、川俣町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、広野町、川内村 |
| 茨城県 | 19 | 日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町 |
| 栃木県 | 7 | 鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町 |
| 群馬県 | 8 | 桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、高山村、東吾妻町、川場村 |
| 埼玉県 | 2 | 三郷市、吉川市 |
| 千葉県 | 9 | 松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、 印西市、白井市 |
| 合計 | 64 |
| 年月日 | 概要 | 指定市町村数 |
|---|---|---|
| 平成24年12月27日 | 福島県昭和村、群馬県片品村、みなかみ町の3町村を解除 | 101 |
| 平成25年6月25日 | 宮城県石巻市を解除 | 100 |
| 平成26年11月17日 | 福島県三島町を解除 | 99 |
| 平成28年3月14日 | 茨城県鉾田市を解除 | 98 |
| 平成28年3月31日 | 栃木県佐野市を解除 | 97 |
| 平成28年9月8日 | 福島県矢祭町を解除 | 96 |
| 平成28年11月29日 | 福島県塙町・柳津町の2町を解除 | 94 |
| 平成29年3月22日 | 群馬県安中市・中之条町の2市町を解除 | 92 |
| 平成31年3月25日 | 福島県会津坂下町、湯川村、会津美里町の3町村を解除 | 89 |
| 令和2年3月16日 | 福島県鮫川村を解除 | 88 |
| 令和3年3月22日 | 宮城県亘理町を解除 | 87 |
| 令和3年12月27日 | 福島県大玉村を解除 | 86 |
| 令和4年3月31日 | 福島県田村市、本宮市、桑折町の3市町を解除 | 83 |
| 令和4年6月30日 | 福島県須賀川市、鏡石町、天栄村の3市町村を解除 | 80 |
| 令和4年9月30日 | 福島県白河市、相馬市、泉崎村、中島村、矢吹町、小野町の6市町村を解除 | 74 |
| 令和5年3月31日 | 福島県福島市、郡山市、二本松市、国見町、三春町の5市町を解除 | 69 |
| 令和5年9月29日 | 福島県伊達市を解除 | 68 |
| 令和6年3月29日 | 福島県いわき市、西郷村、新地町の3市町村を解除 | 65 |
| 令和7年9月30日 | 福島県棚倉町を解除 | 64 |
今後の両地域の方向性
2018年3月までに大規模な除染(いわゆる「面的除染」)が終了し、福島県内においては、2022年3月までに、帰還困難区域を除き、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送は概ね完了しています。
次の段階として、それぞれの地域の指定解除が行われることになります。
除染特別地域に指定されている市町村のうち、帰還困難区域がある市町村については、現在も特定復興再生拠点区域で発生した除去土壌等の輸送や、特定帰還居住区域における除染等が行われており、指定解除を議論できる段階にはありません。
ただ、帰還困難区域がない市町村のうち、田村市については、上述したように、2022年3月に除染特別地域の指定が解除されています。
一方、汚染状況重点調査地域については、前述したように、最大104あった市町村が64まで減少していますが、2018年3月までに既に面的除染が終了していることや、多くの地域において空間線量率が十分低減していることを考えると、特に当初から他の地域と比較して汚染の程度が小さかった地域ではもっと指定の解除が進んでも良いように思えます。
ところが、上に示した地図や表を見ていただくと分かるように、むしろ福島県内における市町村の方が指定解除が進んでいて、2021年12月以降に指定解除された23の市町村は全て福島県内の市町村です。
これには、中間貯蔵施設の存在が大きな役割を果たしていると思います。
中間貯蔵施設については、こちらの記事にも書いたように、福島県内で発生した除去土壌等を受け入れる施設であり、福島県内の汚染状況重点調査地域で発生した除去土壌等については、概ね全て中間貯蔵施設に輸送されています。
一方、福島県以外の市町村については、中間貯蔵施設に相当する施設がなく、発生した除去土壌等については、各除染の現場で保管されているか、仮置場に集約されています。
こうした残された除去土壌等の処理が完了しないことが、汚染状況重点調査地域の指定解除が進まないことの一因になっていると考えられます。
国からは、2025年3月に福島県外で発生した除去土壌に関する埋立処分の基準が公表されており(詳細についてはこちらのウェブサイトをご覧ください)、今後はこの取組を推進していくことが必要かと思います。
この点については、また別の記事で解説したいと思います。
まとめ
今回は、除染特別地域と汚染状況重点調査地域について、その役割分担に関する基本的な考え方や、それぞれの地域の概要や現状、今後の方向性について解説しました。
ちなみに、以上とほぼ同じ内容を動画にもまとめてみましたので、よろしければご覧ください。
日本語版
英語版
本記事の英語版はこちらからご覧いただけます。
今回は以上となります。
ご覧いただき、ありがとうございました。
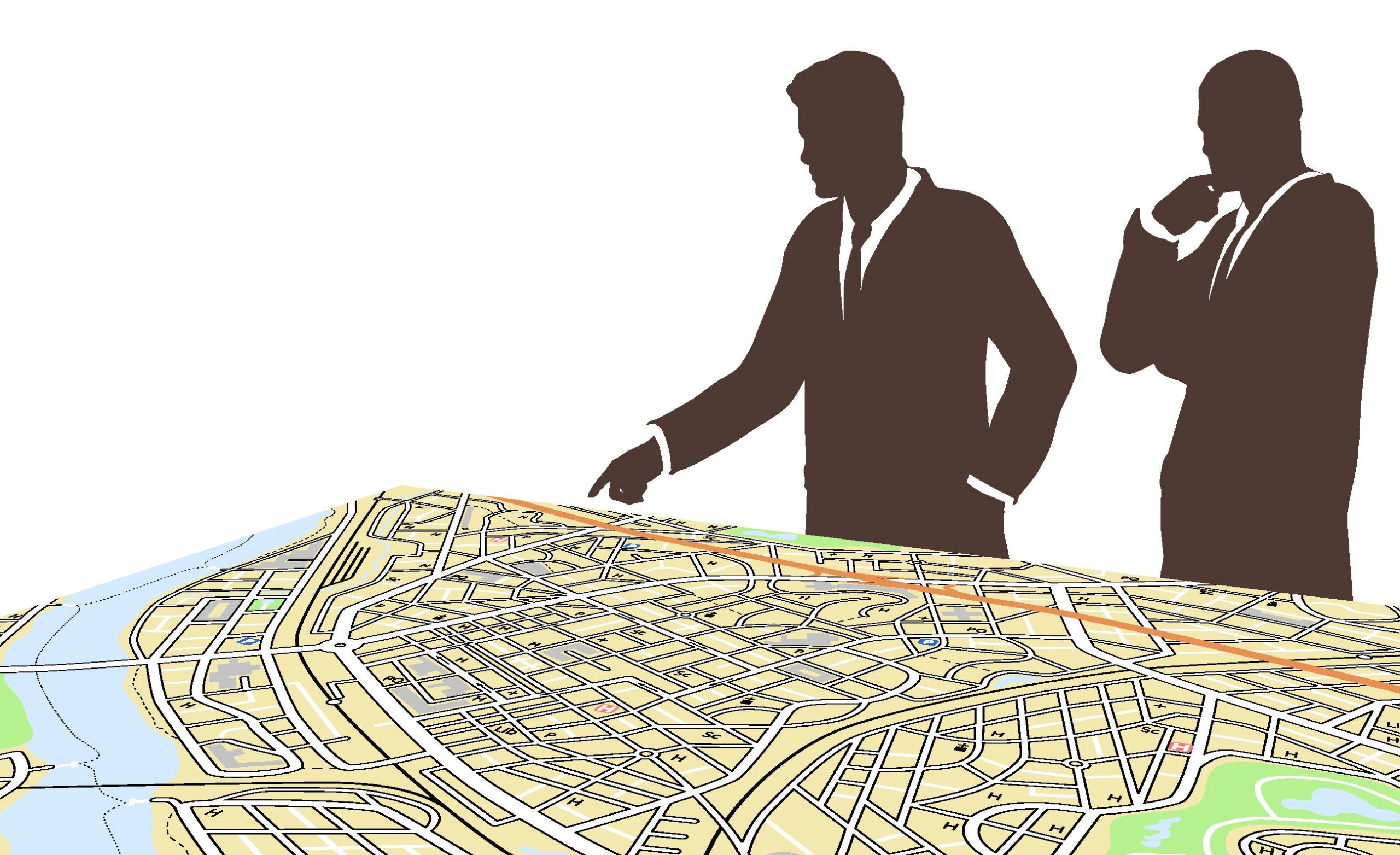


コメント