こんにちは。放射線などについて分かりやすく解説している大地(だいち)です。
こちらの記事では、自然放射線からの影響について、日本や世界全体における影響の程度や、その中でも特に宇宙から地球に届く放射線や、大地から放出されている放射線による影響について解説しました。
今回は、残りの2つ、つまり、呼吸による影響と、食事による影響について詳しく説明したいと思います。
つまり、今回は、
・ 呼吸による自然放射線からの影響ってどんなものなの?
・ 食事による自然放射線からの影響ってどんなものなの?
こういった疑問に答えます。
○本記事の内容
- (呼吸や食事による影響についても解説)自然放射線について(その2)
- 呼吸による自然放射線からの影響
- 食事による自然放射線からの影響
- 鉛210、ポロニウム210
- カリウム40
- 炭素14
- トリチウム
- まとめ
この記事を書いている私は、2011年の福島第一原子力発電所の事故の後、除染や中間貯蔵施設の管理など、継続して放射線の分野での業務に従事してきました。
その間、働きながら大学院に通い(いわゆる社会人ドクター)、放射線の分野で博士号を取得しました。
こういった私が、解説していきます。
(呼吸や食事による影響についても解説)自然放射線について(その2)
それでは、呼吸と食事による自然放射線からの影響について順番に見ていきましょう。
呼吸による自然放射線からの影響
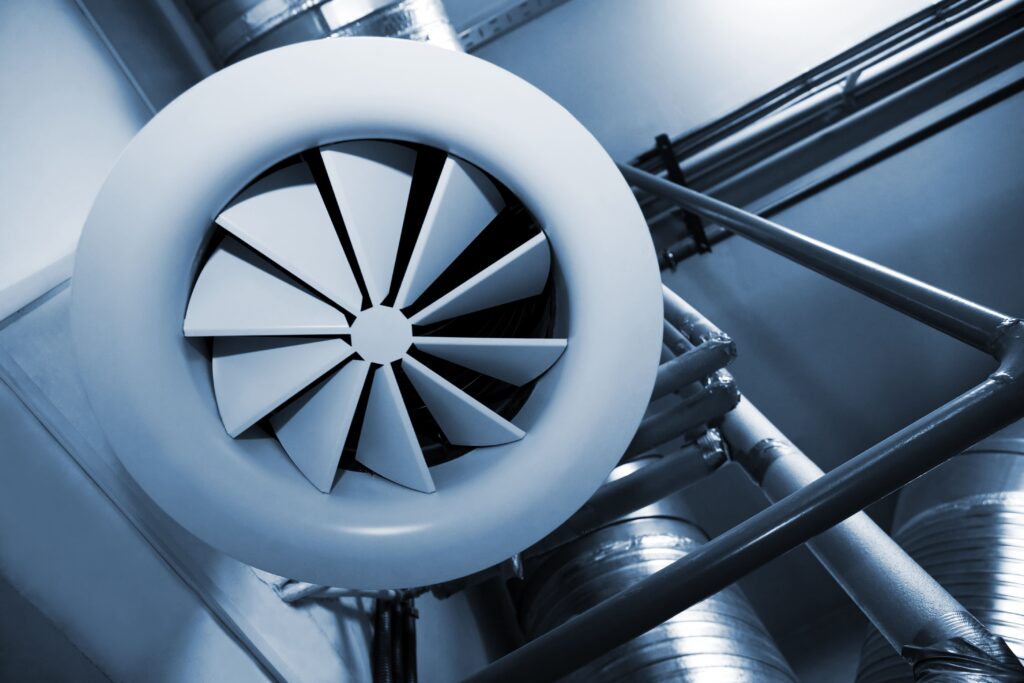
こちらの記事でも解説したように、呼吸を通じて、私たちが普段影響を受けている放射性物質はラドンやトロンです。
ここでは、ラドンは質量数が222のラドン、トロンは質量数が220のラドンのことです。
いずれも、ラドンの放射性同位体なのですが、かつては別々の元素だと考えられていて、その頃の名残で、今でも別々の名前で呼ばれることがあります(質量数、放射性同位体についてはこちらの記事も参照ください)。
こちらの記事でも少し触れていますが、ラドンは地中にあるラジウム226が、また、トロンは同じく地中にあるラジウム224がそれぞれアルファ崩壊することによって生成されます。
いずれも、常温では気体として存在しているため、私たちの周囲の空気中にも存在していて、呼吸を通じて私たちは日常的に体内に取り込んでいます。
その濃度は地域差が大きく、世界で見ると、地質学的な観点(例:土壌に含まれるラジウムの量)や、建物の材料の観点(例:石造、木造)から、例えば、北欧などは濃度が高い傾向にあります(種類にもよりますが、例えば花崗岩には多くのウランやトリウムが含まれています)。
そして、ラドンも、トロンも、空気(平均的な分子量:約29)よりもかなり重い物質であるため、屋内、特に地下のような空間に滞留しやすく、ラドンやトロンの濃度が高い場所では、換気などの対策が必要になる場合もあります。
ちなみに、その量はかなり少ないですが、喫煙によっても、鉛やポロニウムなどの放射性同位体から放出される放射線によって被ばくしますので、タバコは吸わないに越したことはないと思います。
食事による自然放射線からの影響

まず、食品に自然由来の放射性物質が含まれるメカニズムについて簡単にご説明します。
こちらの記事で解説したように、大地には放射性物質が含まれていて、その放射性物質を植物が根から吸収することもあります。
動物については、陸上や、海の生態系の食物連鎖の中で、その放射性物質が捕食者によって取り込まれ、濃縮されていくこともあります。
こうした過程の中で放射性物質を含んだ食品を食べることで、私たちは日常的に放射性物質を体内に摂取しているわけです。
こちらの記事でも解説したように、食事に伴う被ばく線量は、日本では年間約0.99mSvなのですが、その割合は、以下の図のようになっています。
.jpg)
(出典:国連科学委員会(UNSCEAR)2008年報告 及び (公財)原子力安全研究協会「生活環境放射線(国民線量の算定)第3版 増補版」(2024年)より作成)
ー 鉛210、ポロニウム210:0.80mSv/y
ー カリウム40:0.18mSv/y
ー 炭素14:0.014mSv/y
ー トリチウム:0.0000049mSv/y
それぞれの放射性核種について、少しずつ説明していきたいと思います。
鉛210、ポロニウム210
鉛210、ポロニウム210のいずれも、先ほどご説明した、ラドン222がアルファ崩壊する過程で生成される、ウラン系列(ラジウム系列)に属する放射性同位体です。
ラドン222とは異なり、常温では固体として存在しており、それらが地表に沈着したり、河川や海洋に沈降して、陸上や海洋の食物連鎖の中で魚などの生物に吸収され、食事を通じて私たちの体内に日常的に取り込まれています。
ただ、日本人への被ばく線量年間0.80mSvという値は、人の健康に影響を及ぼすような値ではないため、放射線防護の観点からは、食べ過ぎを心配する必要はないと思います(栄養バランスなどの観点からは、偏った食事は健康に良いとは言えないでしょうから、十分に気をつけましょう)。
カリウム40
カリウムは、炭素、酸素、水素、窒素などともに、人体組織を構成するうえで必須の元素の一つであり、自然界に存在するカリウムのうち、おおよそ0.01%は、カリウムの放射性同位体であるカリウム40で、ほとんどの食品に含まれていると言って良いかと思います。
ただ、その放射能濃度は食品ごとに大きく異なっていて、例えば、以下のようになっています。
ー 米:30Bq/kg
ー 牛乳:50Bq/kg
ー 牛肉:100Bq/kg
ー 魚:100Bq/kg
ー ドライミルク:200Bq/kg
ー ほうれん草:200Bq/kg
ー ポテトチップス:400Bq/kg
ー お茶:600Bq/kg
ー 干ししいたけ:700Bq/kg
ー 干し昆布:2,000Bq/kg
干し昆布の放射能濃度が特に高い理由としては、以下のような理由が挙げられます。
・昆布などの海藻の成長期間が長い
・放射性物質を取り込みやすい性質がある
・乾燥によって水分が減少した結果、1kgあたりの放射能濃度が上昇する
ただ、人間の体内のカリウム濃度は一定に保たれるようになっており、日常生活の中で、昆布をたくさん食べたからといって、放射線被ばくの観点から問題になることはないと思います(栄養バランスの観点から気を付けなければならない、という点については鉛210、ポロニウム210のパートで申し上げたのと同様です)。
炭素14
炭素14は、大気中で、宇宙線が窒素原子と衝突することで生成されます。
炭素原子全体に占める割合はごくわずかですが、炭素14は、大気中の二酸化炭素に取り込まれ、さらに呼吸や光合成を通じて動植物の体内に取り込まれています。
動植物が生きている間は、炭素12と炭素14の割合は一定に保たれていますが、死後、炭素14は取り込まれなくなり、放射性崩壊により、その割合は徐々に減少していきます(物理学的半減期:5,730年)。
こちらの記事でも触れましたが、この割合の変化を利用して、その生物が生きていた時代を推定するのが、放射性炭素年代測定です。
トリチウム
トリチウムは、こちらの記事でも解説しましたが、水素の放射性同位体で、福島第一原子力発電所から放出されている処理水に含まれている放射性物質のうち、最も多く含まれているものです。
自然界においては、上に示した炭素14と同様、大気中で、宇宙線が窒素原子と衝突することで生成されます。
発生したトリチウムのほとんどは水分子に取り込まれ、液体として存在していますが、トリチウムが水素原子に占める割合は約1兆分の1〜100兆分の1以下のレベルで、その割合は極めて少なくなっています。
上に示したように、他の放射性核種と比較するとごくごく僅かで、健康面から見ると全く心配する必要はありませんが、この液体として存在しているトリチウムが食事(飲料水)を通じて体内に取り込まれ、私たちに影響を及ぼしているというわけです。
まとめ
今回は、前回からの続きとして、自然放射線に関して、呼吸と食事による影響について詳しくご説明しました。
放射線というと、原子力発電所の事故や病院における治療など、特別な機会に注目を集めがちですが、私たちの身の回りに存在しているものです。
その被ばく量などを知っておくと、そうした特別な機会における被ばく量との比較もできて、放射線に関してより正しい理解ができるかと思います。
ちなみに、以上とほぼ同じ内容を動画にもまとめてみましたので、よろしければご覧ください。
日本語版
英語版
本記事の英語版はこちらからご覧いただけます。
今回は以上となります。
ご覧いただき、ありがとうございました。



コメント